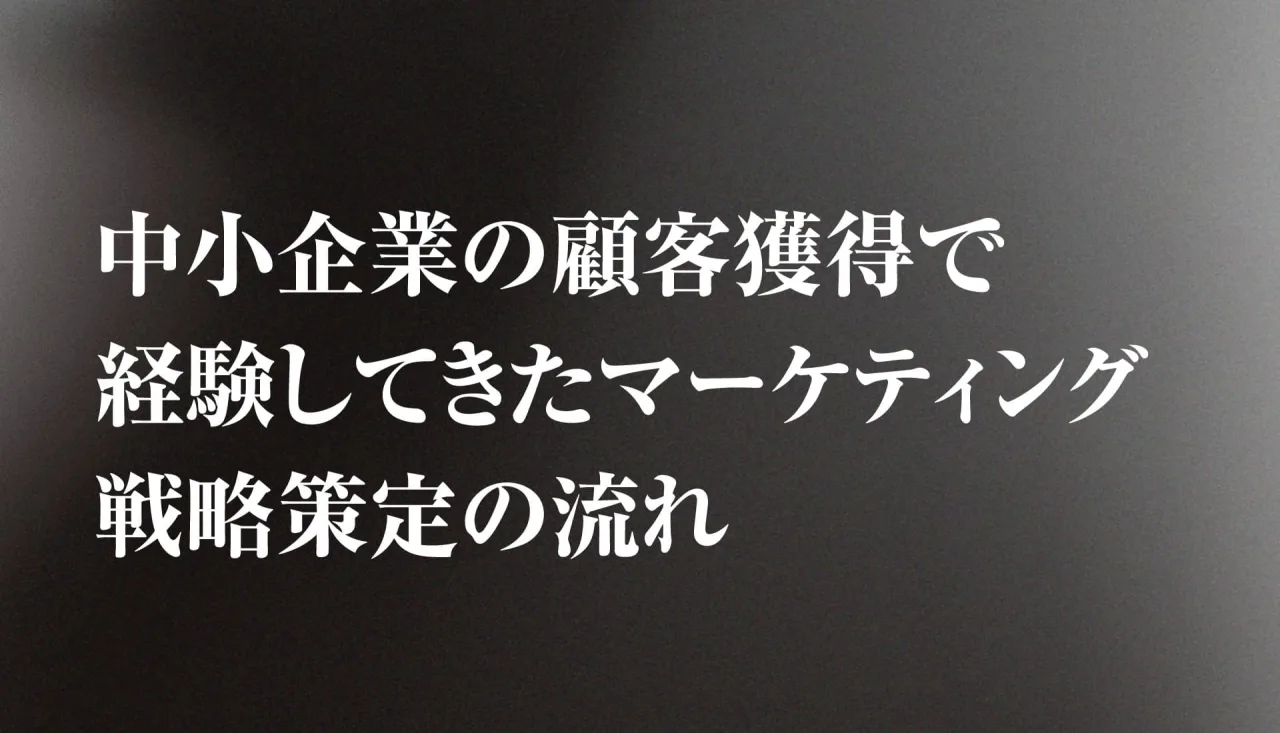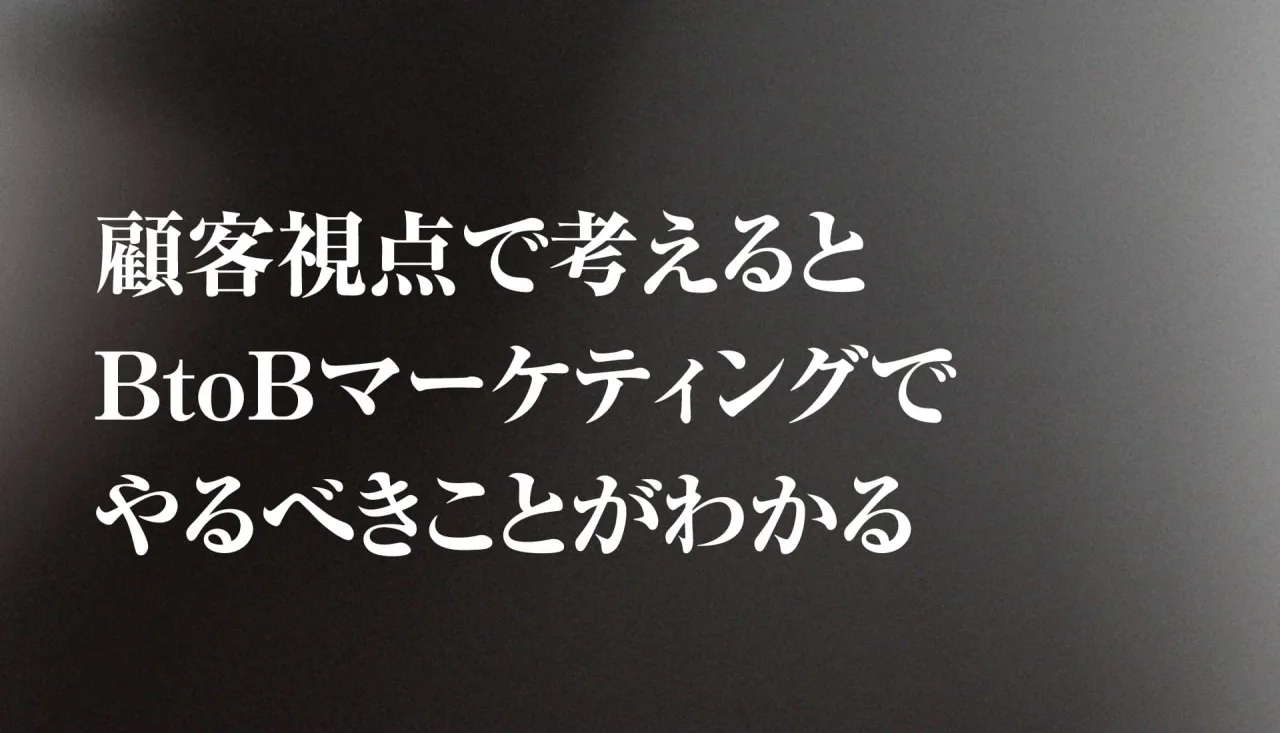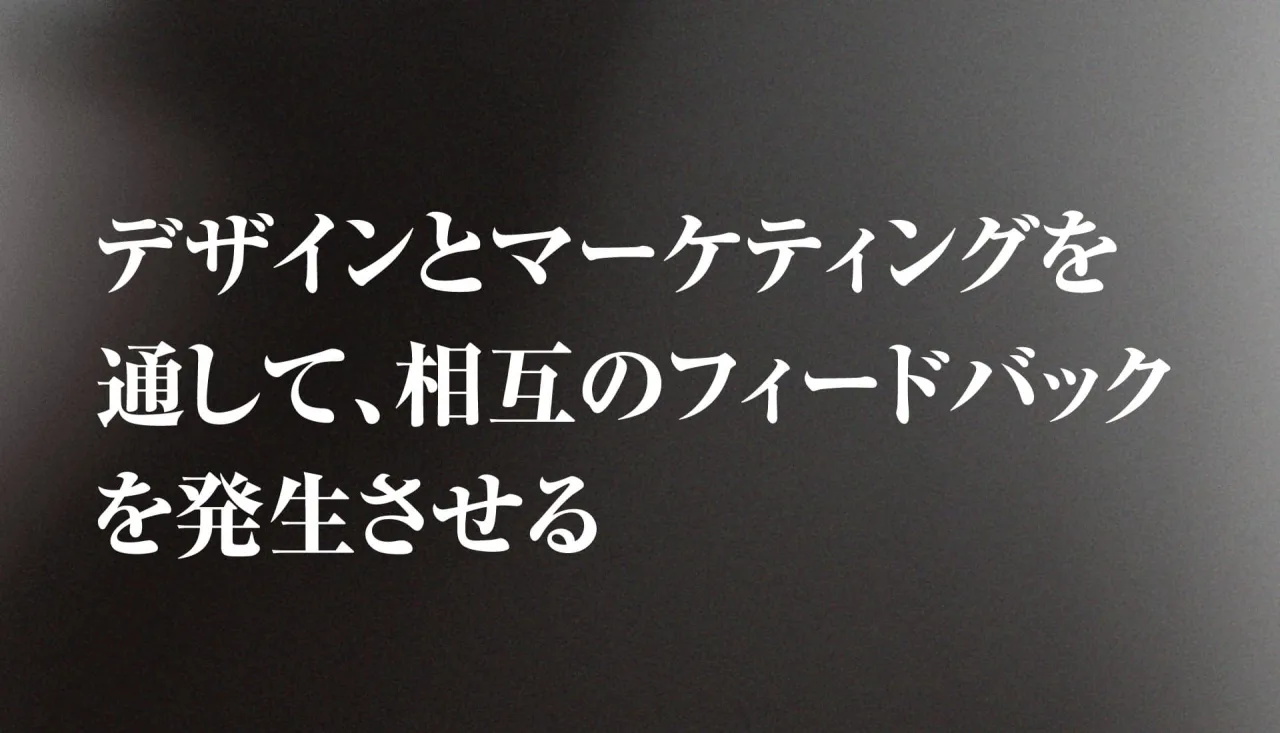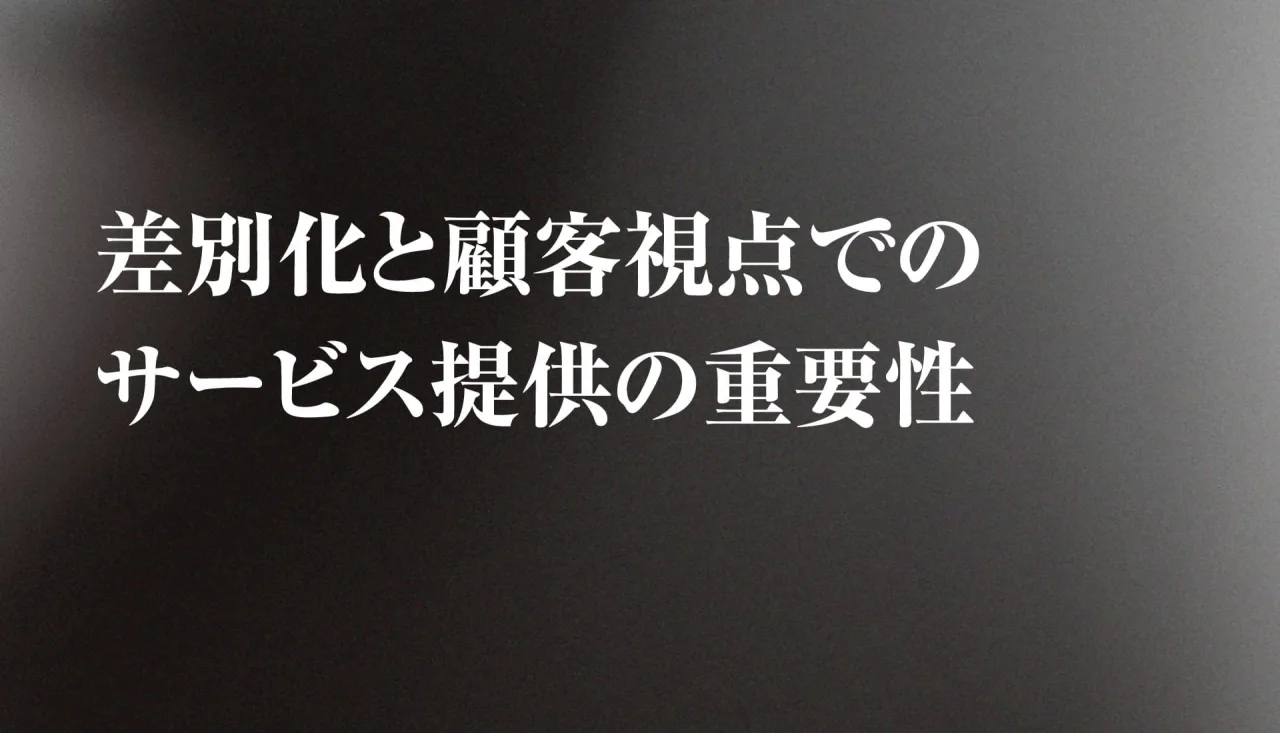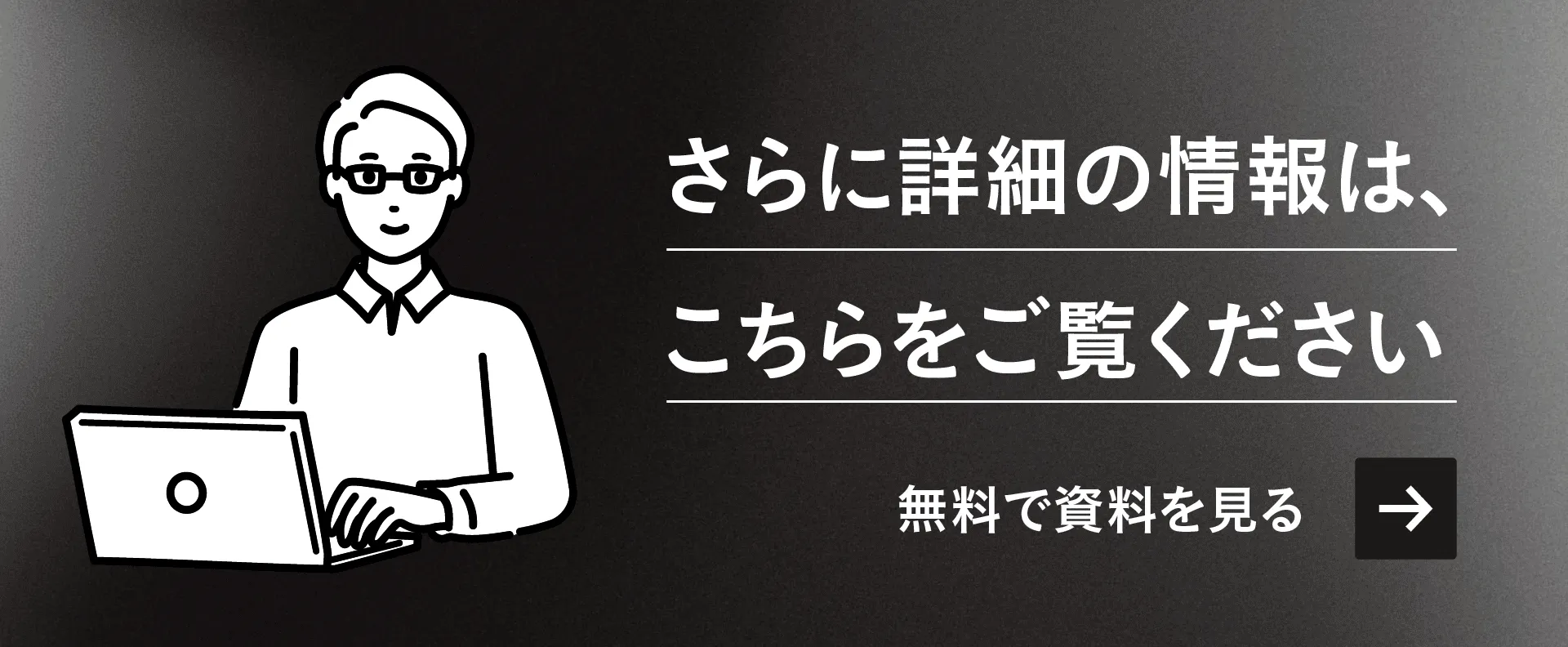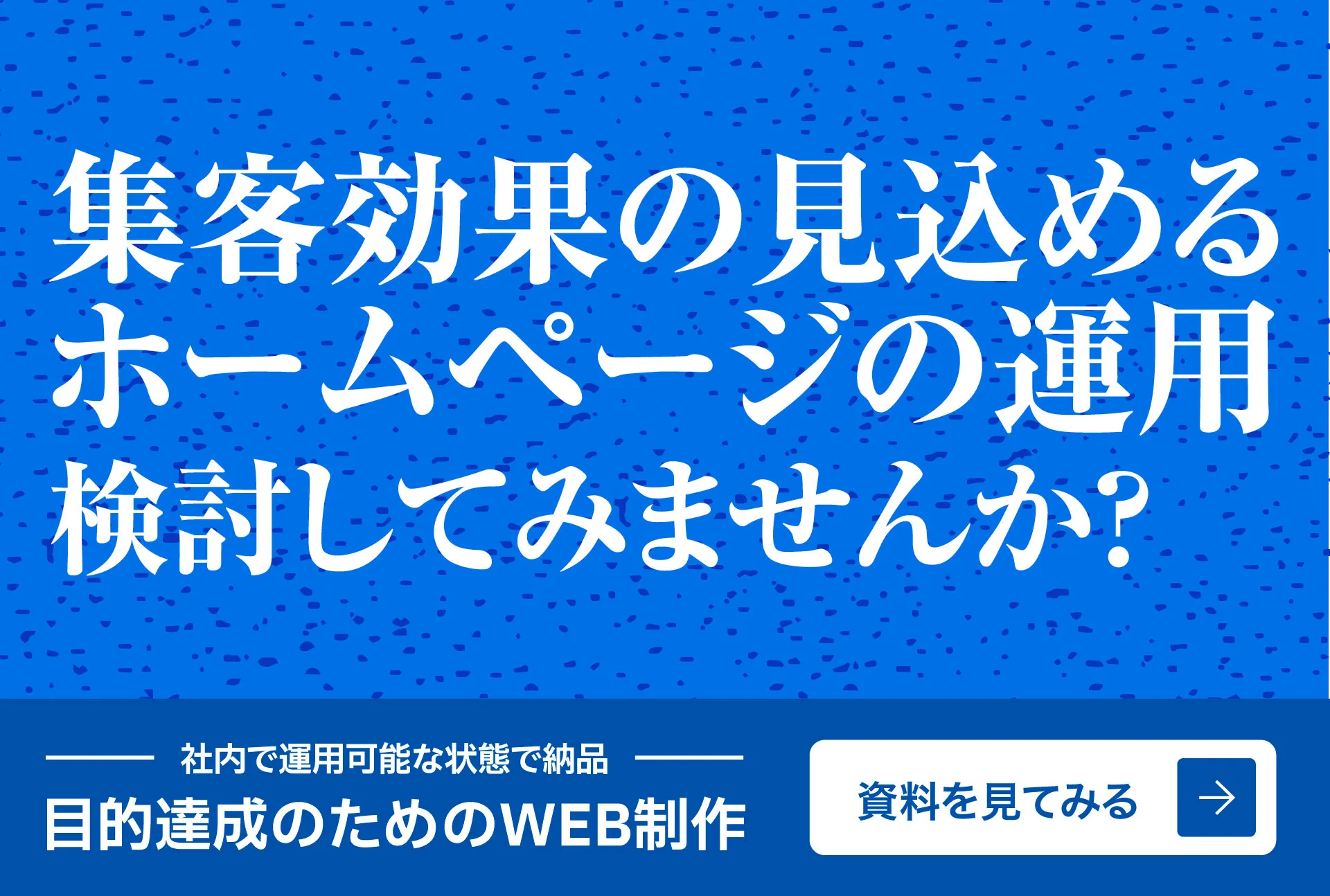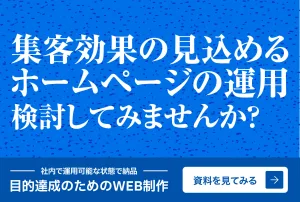目次
WEB担当者の悩み「メルマガってもう古い?」
WEB担当になったばかりの方や、これからデジタルマーケティングを強化しようとしている企業担当者にとって、必ず一度は浮かぶ疑問があります。
「メールマガジンって、いまだに効果があるの?」
日々新たな集客手法が出てきている中で古く見える手法ですが、メールマガジンはいまでも強力なマーケティングチャネルです。
この記事では、最新の数値データを交えながら、メールマガジンのメリットや効果を深堀りし、BtoC・BtoBそれぞれでどんなコンテンツを配信すればよいのか、WEB担当者が実践に移すための具体的なポイントを詳しく解説していきます。
なぜメールマガジンが注目され続けるのか?5つの理由
1. 自社の顧客リストを活用するのでアルゴリズムの影響を受けない
SNSはプラットフォームのアルゴリズム変更で突然リーチが減るリスクがあります。
実際に、FacebookやInstagramのオーガニックリーチは年々減少傾向にあり、企業のSNS投稿がユーザーに届きにくくなっています。
みなさんも日々SNSで広告ばかり目にしているのではないでしょうか。
しかし、メールは登録してくれた顧客に直接情報を届けることができます。
プラットフォームの変更に左右されることなく、安定したコミュニケーションチャネルを確保できるのは、WEB担当者にとって大きな安心材料となります。
さらに、メールアドレスを活用し、他のマーケティング施策との連携も容易になります。CRMシステムとの連携により、顧客の行動を追跡し、より精密なマーケティング戦略を立てることが可能です。
3. パーソナライズとセグメント配信の可能性
現代のメールマーケティングツールは、顧客の属性や購買履歴、ウェブサイトでの行動データに応じてセグメントを分け、最適なメッセージを届けることができます。
例えば、ECサイトであれば以下のようなセグメント配信が可能です:
- 過去に化粧品を購入した女性顧客には新作コスメの情報
- 男性向けガジェットを購入した顧客には関連アクセサリーの提案
- カート落ちした顧客には購入を促すリマインドメール
- 長期間購入していない顧客には復帰を促す特別オファー
このレベルの細かいパーソナライズは、SNSの投稿や広告では実現が困難です。
また、セグメント送信されたメールはCVにも紐付きやすいので、ぜひ導入してください。
4. 測定可能な明確な数値指標
メールマーケティングは、他のマーケティング手法と比べて測定が容易で、施策の効果を数値で明確に把握できます。
主要な指標として:
- 配信数・到達率:どの程度のメールが確実に届いたか
- 開封率:メールを開いて読んでくれた人の割合
- クリック率:メール内のリンクをクリックした人の割合
- コンバージョン率:実際の購買や問い合わせにつながった割合
- 登録解除率:メルマガを解除した人の割合
これらの数値を継続的に分析することで、配信内容や配信タイミングを最適化し、成果を向上させることができます。
ちなみに、「週に送り過ぎると迷惑だと思われ、解除率が高まるのではないか」と心配される企業もいますが、多くのビジネスマンは毎日数多くのメールを受信しているので前日のメールのことは覚えていません。
実際弊社が支援している企業でも送信回数と解除率には相関関係が見られませんでした。
どんどん送って告知しましょう。
4. オートメーション化によるWEB担当者の効率化
現代のメールマーケティングでは、自動化(マーケティングオートメーション)の活用が主流になっています。一度設定すれば、顧客の行動に応じて自動的に最適なメールが配信される仕組みを構築できます。
代表的な自動化例:
- ウェルカムシリーズ:新規登録者に段階的に会社やサービスを紹介
- カート放棄メール:商品をカートに入れたまま離脱した顧客への自動リマインド
- 誕生日メール:顧客の誕生日に特別オファーを自動配信
- リエンゲージメントメール:長期間反応がない顧客への再活性化メール
これにより、WEB担当者は日常的な配信作業から解放され、より戦略的な企画に時間を割くことができます。
特にECサイトではメールの自動化による顧客アプローチの回数が売上に直結します。
活用して施策を回していきましょう。
データで見ても「まだ効果が出る」と言える
開封率とクリック率の業界別データ
国内の全体平均
- 開封率:31.75%(アメリカ:20.53%)
- クリック率:1.30%(アメリカ:0.61%)
こう見ると国内におけるメールマガジンは健在だと言えるでしょう。
業界別の開封率(2024年データ)
- 製造/物流/エンジニアリング:17.03%
- 小売/消費サービス:24.28%
- 医療:28.14%
- コンサルタント/HR/人材:20.33%
- NPO/行政サービス:32.65%
- フィットネス:24.46%
情報収集の手段としても上位
Benchmarkが出しているレポートを元に、上位から並べます。
- LINE:57.5%
- メールマガジン:49.3%
- X:41.5%
- Instagram:36.7%
LINEに次ぐ割合でメールマガジンが情報収集の手段として認知されていることが分かります。
ここからはBtoCとBtoBそれぞれどういった活用方法があるか見ていきます。
特にBtoBは配信曜日によって開封率も変動するというデータもございますのでチェックしてみてください。
BtoCにおけるメールマガジン活用戦略
配信すべきコンテンツ例と具体的手法
1. セール・クーポン情報(期間限定・会員限定の特典)
お得なキャンペーンを告知することで即効性のある効果が見込めます。
件名のコツとしては「今だけ」「限定」「残り○時間」などの緊急性を演出することで開封率が上がることもあります。ブランドの世界観に合わせて活用してみてください。
2. 新商品・人気商品紹介(ランキング形式が効果的)
ストーリーテリングを取り入れた打ち出しも効果的です。
商品開発の背景や使用者の声を織り交ぜた今鉄を発信することで商品詳細ページなどでは知ることができない付加価値を感じていただけるでしょう。
3. 季節やイベントに合わせた特集
一般的な行事に合わせた訴求は今でも大きな効果が見込めます。
アパレルなどは季節ごとにおすすめのアイテムをまとめたコンテンツを配信しますし、クリスマスシーズンであればおすすめのギフトコンテンツなども作成できます。
年間のイベントカレンダーを作成し、自社のブランドがどんなタイミングで発信するべきかを整理してもいいかもしれません。
4. ユーザー参加型コンテンツ
こちらはSNSと連携し、ユーザーに商品を使った投稿をしてもらうことでPRを行うなどの取り組みです。
一般的には「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」と呼ばれる手法ですが、告知をメールマガジンを通して行うことで協力を得やすくなるでしょう。
「投稿してくれた方には5%OFFクーポンをプレゼント」などのインセンティブ設計も必要です。
5. ライフスタイル提案型コンテンツ
インテリアや食品を扱うブランドで特に多いのが提案型のコンテンツです。
機能的な訴求だけでなく、それを使うことでこんな生活ができそう、〇〇さんも使っているのか、といった商品の付加価値をあげるような手法です。
BtoBにおけるメールマガジン活用戦略
配信すべきコンテンツ例と詳細な手法
1. 業界トレンドや市場レポート(知識提供で信頼獲得)
調査データを活用した解説コンテンツ、レポート結果などの配信は一定の需要があるかと思われます。
BtoBは意思決定が段階的に行われる分、数値化されたコンテンツは読み手にとっても親切な情報と言えるでしょう。
また、業界の最新動向を先取りして情報提供(例:2024年度 IT投資動向調査レポート〜DX推進の現状と課題〜)なども有効です。
競合との差別化を図りたい企業の目線で考えると、業界全体の最新情報はキャッチアップしたいはずです。
2. 導入事例・お客様の声(信頼と具体性を提示)
こちらはホームページに掲載している情報を改めて発信するケースもございますが、「弊社サービスでコスト30%削減を実現」「業務効率50%向上」など具体的な効果を発信できると読み手としてもイメージがつき易くなります。
課題解決のストーリーをBefore→After形式でわかりやすく紹介したり、顧客インタビュー記事を発信するのも有効な手段と言えます。
3. ホワイトペーパーや資料DLの案内(リード獲得)
一定のセグメント管理が必要という前提ですが、ホワイトペーパーをメールマガジン経由で送るのも一つの手です。
契約前の見込み顧客へのプッシュにもなりますし、既存顧客に対してもクロスセルの提案になったりするので有効です。
4. ウェビナーや展示会の告知(商談機会を増やす)
BtoBのメールマガジンの活用方法でおそらく最も多いのはウェビナーへの案内ではないでしょうか。弊社も毎日何件も来ますが、裏を返せばそれくらい効果があるということです。
私自身、いつもは無視していますがニーズに刺さったものがあれば開いてウェビナー参加したりします。数を打つという点ではリソースの具合を見てぜひ取り入れたい手法です。
5. 新機能リリース情報(既存顧客のエンゲージメント強化)
SaaS系のサービスに多いのがこちらのリリース配信です。
機能改善や不具合のお知らせなどの業務的なものもあれば、アップデートによる新機能追加と共にアップセルを狙った告知もできます。
受託系の企業でも「新サービス始めました」といったような内容で活用することで、十分効果が見込めます。
BtoB特有の配信戦略とタイミング
BtoBは曜日によって開封率が変動する傾向にございます。また、読み手の役職によっても見られるべきポイントが変わりますので意識してコンテンツを作りましょう。
配信曜日・時間の最適化
- 火曜日〜木曜日の午前10時〜午後4時が最も開封率が高い
- 月曜日:週の始まりで忙しく、開封率が低下
- 金曜日:週末モードで業務関連メールへの関心が低下
決裁フローを意識したコンテンツ設計
- 担当者向け:技術的な詳細、導入メリット、競合比較
- 管理者向け:ROI、導入事例、リスク対策
- 経営層向け:戦略的価値、市場優位性、将来性
WEB担当者が押さえるべき配信の実践ポイント
件名(タイトル)作成のポイント
BtoC向け件名の黄金律
- 感情に訴える表現:「今だけ50%OFF!」「見逃し厳禁」
- 数字の活用:「3日間限定」「先着100名様」
- 個人化:「○○様へ特別なご案内」
- 疑問形:「まだ夏の準備できていませんか?」
BtoB向け件名の黄金律
- ベネフィットの明確化:「営業工数を30%削減する方法」
- 専門性のアピール:「IT部門必見」「製造業向け」
- 数値による具体性:「導入企業500社突破」
- 緊急性と限定性:「申込締切迫る」「限定公開資料」
同じ内容でも件名を変えることで開封率が大きく変わります。定期的にA/Bテストを実施し、最も効果的な件名パターンを見つけることも大切です。
モバイル最適化の必須ポイント
現在、メールの約50%がスマートフォンで開封されています。
モバイル対応は必須中の必須です。
技術的な最適化ポイント
- レスポンシブデザイン:画面サイズに応じた自動調整
- フォントサイズ:最小14px以上で可読性を確保
- ボタンサイズ:最小44px×44pxでタップしやすく
- 画像の最適化:読み込み速度を考慮したファイルサイズ調整
コンテンツ設計の最適化
- 短文での要点整理:長文は避け、重要な情報を先に配置
- 縦スクロールを意識した構成:重要な情報を上部に配置
- CTA(Call To Action)の明確化:1つのメールに1つの明確なアクションを設定
セグメント配信で成果を最大化する方法
メールマガジンを活用するにはセグメントの管理が欠かせません。
より顧客のニーズに沿ったコンテンツを配信するため、どういう基準でセグメントを分けるのかを検討しましょう。
多くの企業で用いられるセグメント例をまとめました。
行動ベースセグメント
- アクティブユーザー:過去30日以内にメールを開封・クリックした顧客
- ドーマントユーザー:過去3ヶ月以上反応がない顧客
- ヘビーユーザー:頻繁に購入や問い合わせをする顧客
属性ベースセグメント
- デモグラフィック:年齢、性別、居住地域
- サイコグラフィック:興味・関心、価値観、ライフスタイル
- ビヘイビア:購買履歴、ウェブサイト閲覧履歴、アプリ利用状況
他チャネルとの戦略的連携で効果を倍増
オムニチャネル戦略の構築
- メールで興味喚起 → SNSで話題化 → LPでCVという一連の流れを設計
- メールでイベント案内 → リマインドSMSで参加率アップ
- 広告でリーチ拡大 → メールでナーチャリング → 営業でクロージング
データ連携による精密なターゲティング
- CRMシステムとの連携:顧客の購買履歴と連動したパーソナライズ配信
- ウェブサイト行動データとの連携:閲覧ページに応じたフォローアップメール
- SNSエンゲージメントとの連携:SNSでの反応度に応じたメール配信頻度調整
おすすめの配信ツール
メールマガジンを活用した施策を行う上でおすすめのツールを3つご紹介します。
これまで弊社でも使用してきましたが、社内の状況や必要な機能に合わせてご活用ください。
| 項目 | Benchmark | Mailchimp | HubSpot |
| 無料プラン | 連絡先500件/月3,500通 | 連絡先500件/月1,000通(1日500通上限) | 月2,000通まで。HubSpotのロゴ表示あり。 |
| 日本語対応 | 日本語サイト/多言語サポート | 日本語UIは原則対象外 | 日本語UI・サポート情報あり |
| セグメント | 基本セグメント可 | 豊富なセグメント機能(プランで差) | CRM一体で高度セグメント |
| CRM連携 | 連携多数/簡易CRMあり | 外部連携が強み | CRMメインのツール |
比較まとめ
- Benchmark:
シンプルなデータ管理にCRM連携で自動化したい方に最適。簡易的に施策を立ち上げたい企業におすすめです。データ測定に必要なツールも無料の範囲で使えます。 - Mailchimp:
素早く導入でき、標準的な形でのデータ取り込み・管理で十分な場合に適しています。柔軟性は小さめで、UIが日本語に対応していないので慣れが必要です。 - HubSpot:
高度なデータ構造管理、AIによる補完、豊富な連携により「顧客中心の情報活用」を重視する企業にベストです。特に、Sales/マーケティングを深く統合したプロセス設計をしたい場合は最優先の選択肢になります。
実践的な始め方:WEB担当者のためのステップバイステップガイド
「まずは始める」でも大丈夫なのですが、施策の改善や報告義務としても仮説と検証方法を設定してから進めることをおすすめします。
Step 1:現状分析と目標設定
現状の整理
現在の顧客データベースの規模と質の確認や過去のメール配信実績がある場合はそのデータの分析を行いましょう。
競合他社のメールマガジンに登録してみるもの有効な手段です。
(弊社では登録しすぎて様々なサービスから非常に多くの日々通知がきます。)
分析したデータから「3ヶ月で月間売上の10%をメール経由にする」「開封率を1%改善する」などの目標を立ててみましょう。
Step 2:コンテンツの作成
施策を始めてみると痛感しますが、ネタの考案や文章や画像の作成と、意外と工数がかかって嫌になってくることもあります。
そういった状態を回避するためにあらかじめ配信カレンダーを作成してみましょう。
おおよそのネタのイメージがつくだけで負担が軽減されるはずです。
年間配信カレンダーの作成
- 季節イベント:年間を通じた販促タイミングの整理
- 商品リリース:新商品・サービスの発表スケジュール
- 業界イベント:展示会、カンファレンス等の業界動向
また、切り口もおおよそ決めておくことで「ネタ×コンテンツタイプ」と考えることができ、継続的に良質なコンテンツ生成が可能になります。
コンテンツタイプの定義
- 情報提供型:業界ニュース、トレンド解説(40%)
- 商品紹介型:新商品、おすすめ商品の紹介(30%)
- エンゲージメント型:アンケート、キャンペーン(20%)
- 教育型:使い方、活用事例の紹介(10%)
Step 3:リスト構築と初期配信
配信先のリストを拡充する方法についても検討していきましょう。
メールマガジンは母数が多いほど効果を発揮します。
リスト獲得は営業の仕事と、割り切りすぎず、WEBマーケティングの範囲で貢献できそうなことを検討してみましょう。
オプトイン獲得の仕組み構築
- Webサイトでの登録フォーム設置:トップページ、サービス紹介ページ
- リードマグネットの作成:ホワイトペーパー、eBook、チェックリスト
- 既存顧客への移行案内:従来の連絡手段からメルマガへの誘導
商材によってはステップメールと言われる手法も効果的です。
特にツール系の商材であれば使い方などの情報は必ず届けたいもの。ステップメールを自動フロー化させることで効果的に顧客接点を取ることができます。
初回配信とPDCAサイクルの開始
- ウェルカムメールの設定:登録直後の自動配信メール
- 定期配信の開始:週1-2回の定期配信スケジュール
- 効果測定と改善:開封率、クリック率の継続的な分析
Step 5:施策の改善について
メールマガジンは回数を重ねるごとにデータが蓄積されていくのが面白い点です。
開封率やクリック率に影響する変数は非常に多いですが、その中で本質的に自社の事業に影響のある指標を導き出し、改善するのが腕の見せどころです。
以下に改善活動の代表例をピックアップしました。
- A/Bテストの実施:件名、配信時間、コンテンツ構成の最適化
- セグメント配信の導入:顧客属性に応じた配信内容の個別化
- 自動化シナリオの構築:購買行動に応じた自動フォローアップ
メールマーケティングの法的・倫理的配慮
メールマガジンは個人情報を取り扱う施策のため、データ管理と規則順守に関しては丁寧に対応しましょう。
特定電子メール法への対応
必須記載事項の確認
- 送信者の氏名または名称:会社名、部署名の明記
- 送信者の住所:本社または事業所の所在地
- 苦情・問い合わせ連絡先:電話番号またはメールアドレス
- 配信停止方法の明示:簡単に配信停止できる手順の説明
同意取得の適切な方法
- 事前同意の原則:配信前の明確な同意取得
- 同意内容の明確化:何の目的でメールを送信するかの説明
- 同意撤回の容易性:いつでも簡単に配信停止できる仕組み
メールマガジンの効果を高めるのに役立つスキル
もしメールマガジンの効果に伸びやなむタイミングがありましたら、下記のスキルを意識してもいいかもしれません。
メールマガジンは複合的なスキルから成り立っています。今自分に足りていないスキルを俯瞰してみましょう。
必要なスキルセット
技術的スキル
- HTML/CSS基礎:メールテンプレートのカスタマイズ
- マーケティングオートメーション:各種ツールの操作スキル
- データ分析:Google AnalyticsやMAツールでの効果測定
マーケティングスキル
- 顧客心理理解:購買行動心理学の基礎知識
- コピーライティング:クリックされる件名・本文作成
- セグメンテーション:効果的な顧客分類手法
プロジェクトマネジメントスキル
- 施策企画力:年間を通じた戦略的な企画立案
- 部署間調整:営業・システム部門との連携推進
- 効果検証:PDCAサイクルの継続的な実行
メールマガジンはまだまだ現役、たくさん送ろう
この記事を通じて、メールマガジンが現在でも極めて有効なマーケティング手法であることが明確になったのではないでしょうか。
メールマガジンの変わらない価値
- BtoCでもBtoBでも高い効果を発揮:業界を問わない汎用性
- 最新データでも証明されるROI30〜40倍という圧倒的な投資対効果
- 自社で完全にコントロール可能なマーケティングチャネル
成功の鍵となる要素
- 戦略的なコンテンツ設計:読者にとって価値のある情報提供
- データドリブンな最適化:継続的な測定と改善
- 他チャネルとの効果的な連携:オムニチャネル戦略の一環として活用
WEB担当者にとっての意義 SNSのアルゴリズム変更や広告費の高騰に左右されることなく、自社でコントロールできる安定した顧客接点として、メールマガジンは今後もWEB担当者が必ず押さえておくべき王道のマーケティング手法です。
特に2024年以降は、AIを活用したパーソナライズやマーケティングオートメーションの進化により、これまで以上に効率的で効果的なメールマーケティングが実現可能になっています。
「古い手法」と誤解されがちなメールマガジンですが、実際には最新技術との組み合わせで更なる進化を続けている現役のマーケティング手法なのです。
まずは小さく始めて、データを見ながら継続的に改善していく。
そのプロセスを通じて、メールマガジンの真の価値を実感していただけるはずです。
WEB担当者の皆様にとって、この記事が効果的なメールマーケティング実践の第一歩となれば幸いです。